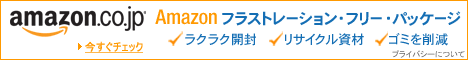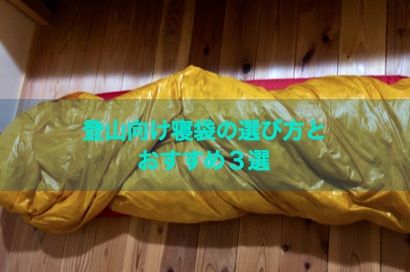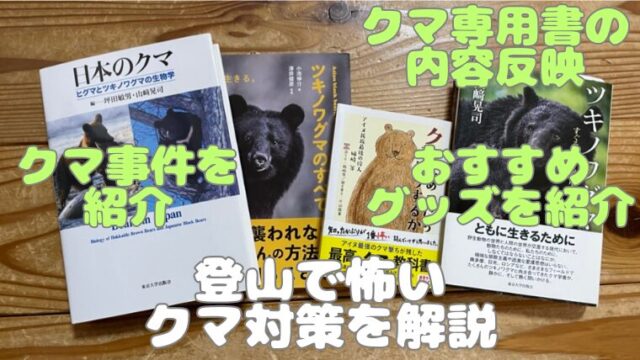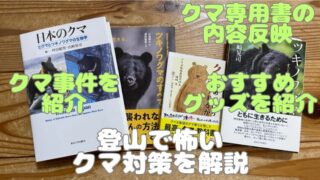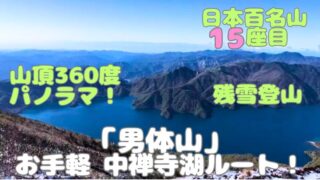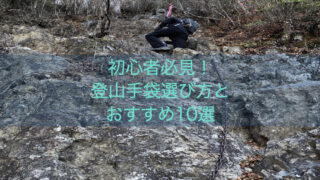登山で守るべきマナーを知らない方
登山を始めたいが、マナー違反で怒られたくない方
マナーを理解して、快適に登山をしたい方
登山をしたいけど、マナー違反で怒られるのが怖いよ…。
どんなマナーがあるのかな?
登山にはさまざまマナーがあることはご存知でしょうか?ただ、初めて登山される方はどのようなマナーがあるのかわからないですよね。
ハムちゃん、登山マナーは難しくないよ。普通に守れることばかりだから大丈夫!200以上の山を登った事のある むらが、登山マナーを紹介します。
マナーには、安全に登山するためのもの。間違えることで自分の命や周りの人の命も危険にさらしてしまう恐れもあるので、まずはマナーをしっかり確認しておきましょう。また、マナーを守ることで愛する自然を守ることにもつながります。
この記事を読むことで山の基本的なマナーを覚えることができます。みんなが登山を快適にするために、一定の基準が必要です。基礎知識として山のマナーを覚えておきましょう。
最低限知っておきたい登山マナー15選
①登山保険に加入する。
山登りを始めるなら、保険に入ることがマナーの1つです。
不運にも自分が遭難してしまった場合、捜索をしてもらう際に多額の費用が掛かります。保険はその費用を賄うことができます。
特にご家族がおられる方は、遭難すると精神的につらいのに費用の面でも多大な迷惑がかることを認識してしっかりと備えることが必要です。
民間の登山保険には、登攀や雪山など 本格登山を対象にした保険と軽登山やハイキングのような 危険度が少ない登山を対象にした保険の大きく分けて2種類があります。
両者の線引きは保険会社によっても異なります。補償内容もさまざま存在しますので、保険会社に問い合わせて、自分の登山スタイルにあった保険を選びましょう。
自分はjRO 日本山岳機構に加入しています。

②登山届けを必ず提出する。
登山届けを必ず出しましょう。
山で遭難してしまうと、周囲に誰もいないし携帯も通じないです。誰かに遭難を気づいてもらい、アクションを起こしてもらうしかありません。
登山届は、警察が捜索依頼を受けたときに登山届けがあれば捜索すべき範囲を特定しやすく、初動捜査が早くなり救助される可能性が高まります。行く可能性のあるルートはしっかりと記入しましょう。
登山届は、登山口のポストに投函するほかに、管轄する警察署へ郵送やFAXで提出する事もできます。最近では「Compass」というインターネットで全国の山域の登山届を提出する事ができ、下山通知機能もあり安否確認もできます。利用は無料なので出し忘れ防止もできるため、使用する事をおすすめします。
自分はどんな低山でも必ず、Compassで登山届を提出しています。

アプリの最新はコンパスEXになっています。
③レベルに合った登山をする
絶対に無理をしない登山をするのが重要です。
山で無理をすると、自分の体調に異変が起きて遭難してしまうことがあります。技術が伴っていないのに鎖場に挑戦すると滑落してしまいます。
自分の経験になりますが、今まで5時間程度しか歩いたことがないのに、8時間以上のコースを挑戦した際に5時間半くらいから膝が痛くなり、まともに歩けなくて大変でした。
登山を楽しく安全にするために、少しずつ経験を積んでいくことをおすすめします。

④ゴミは家まで持ち帰る。
登山中に出たゴミは家まで持ち帰りましょう。
山へ持ち込んだゴミを山小屋のゴミ箱に捨てるのも厳禁です。できるだけゴミになるものは持って行かないように配慮が必要です。
自分はモンベルのガベッジバックを利用しています。液漏れやにおいの心配がなく、ゴミをしっかりと持ち帰ることができます。

⑤汚水や残飯を捨てない。
山での自然を守るために汚水や残飯を捨てないようにしましょう。
微生物が少なく分解の遅い高所で汚水を流すと、下流域にも影響が出てしまいます。残飯も捨てないようにしましょう。
残飯を捨てると、熊が食べてその場所に住み着いて人を襲うなど、生態系にも影響が出るのでNG。歯磨き粉や化粧落としの洗顔なども悪影響がありますので注意が必要です。
歯磨き粉は成分としては化学物質がほとんどで、自然界で分解されません。歯磨き粉の中には、清掃助剤としてプラスチック製のマイクロビーズが使われており、生態系への影響は大きいです。
山で使用できる歯磨き粉もあります。自分も持っているのがオーラルピースでケミカルフリーになっていますので検討してみてはいかがでしょうか?
【PR】

⑥植物や石などむやみに採取しない。
生態系保全のため、少量であっても持ち帰るのはNGです。
また、同じ理由で外来の植物や動物を山に持ち込まないのも気を付ける必要があります。国立公園内での採取は条例違反です。
高山には珍しい種類の花やきれいな花があり、登山中に見かけたら登山の記念にもって帰りたいと思う気持ちになるのはわかります。山でとっていいのは写真だけ。自分の大好きな自然を守るためにも必ず守りましょう。

⑦登山道から外れない
登山道は安全に歩けるように整備されています。登山道を外れることで、滑落や転落のリスクが高まります。
高山植物が豊富な場所では、登山道を外れて歩くことで植物が死滅して自然破壊につながります。登山道から不用意に外れないようにしましょう。

⑧登山道をふさがない。
登山道をふさいでの休憩や写真撮影はマナー違反です。
特にグループ登山をしているときは要注意。みんなで楽しく登っているといつの間にか広がって歩いてしまい、登山道をふさいでしまいます。後ろから早い方が来られた際は、最後尾の方がグループメンバーに声をかけ、安全にかわせる場所に退避して道を譲ってあげましょう。

⑨山のトイレは、ルールを守る。
山に設置されたトイレにはいろいろな形式のものがあります。利用する際は、注意書きをよく読んで、ルールを守りましょう。
よくあるのが、使用済みのトイレットペーパーは便器に捨てずにゴミ箱に捨てて、利用後はバケツに汲んである水を便器に流す方式です。そのほかに微生物で分解するバイオトイレです。利用方法を間違うと使えなくなってしまうのでルールは守りましょう。
山のトイレでは、利用料として料金箱が設置されているところがあります。金額は場所により様々で100円から300円くらいです。山のトイレは特殊な環境にあるため、維持管理するのに多大のお金がかかります。
利用の際にはきちんと払えるように、100円玉を5枚は携帯しましょう。

⑩早発ち・早着きを心がける。
テント泊や小屋泊をする際に注意が必要なマナーです。
少なくとも日没の2~3時間前には到着し、テント泊であればテントの設営を終え、食事をし、日没後には就寝するというサイクルが基本となります。山小屋は明るいうちに到着し、明日の登山準備を早めに済ませましょう。
早発ち・早着きは泊りだけではなく、日帰り意識しましょう。早い時間登山を開始する事で、トラブルがあった際でも時間に余裕ができ遭難するリスクを低減できます。

⑪登山中は周囲への配慮・注意を怠らない。
特にグループ登山をしていると、自分たちの世界に入ってしまい廻りが見えなくなってしまいがちです。周囲を意識して、他の登山者の迷惑にならないようにしましょう。
そのほかにも大音量でラジオを流して歩くことはマナー違反です。静かな自然を楽しみに来ている方もいますのでやめましょう。
周囲の音が聞こえないため、落石や野生動物などの危険に気づけず、非常に危険な状態になりますので、心がけましょう。
⑫石を落としてしまったら、下に向かってすぐに声をかける。
登山をしていると、気を付けて歩いても石を落としてしまうことがあります。小さい石でも落下していくことで凶器に変わってしまい、大事故につながります。
石を落としてしまったときや落石を見かけたら、すぐに「ラーク」と叫び、大声で知らせましょう。
自分も過去に富士登山で大きな岩が落ちてきことがあります。その際に下にいた外国人登山客の方に声をかけることで、避難してもらえた経験があります。慣れないと忘れがちですが、必ず実行しましょう。

⑬登り優先・道を譲る際は山側で待つ。
登山道は基本的に登り優先ということが暗黙のマナー。これは、登りの人は体力的にきつい状態であり配慮するためと、下りの人のほうが相手に気づきやすく、すれ違う場所も探しやすいためと言われています。
ただ、状況により臨機応変に対応が必要です。例えば、ツアーで大人数で登山している場合や、人気の山で登りの人数があまりに連続したら、下りの人はなかなか前へ進めない状況になります。そんなときは互いに声かけし、譲り合いましょう。
道を譲る際は、山側で待機しましょう。谷側で待っていると、すれ違う際にザックが当たったり、人がよろけてきたらバランスを崩し滑落してしまいます。

⑭すれ違う登山者に挨拶する。
登山道ですれ違う際は挨拶する事がマナーとなっています。
挨拶には意味があり、万が一遭難者が出た際に、挨拶をしていることで、すれ違った登山者の記憶に残っていて、捜索の手がかりになります。
挨拶をする際はしっかりと挨拶をすることが相手のためにもなり、自分のためにもなります。山での挨拶は、ほんとに気持ちが良いものですので、実践してみてはいかがでしょうか。
⑮携帯トイレを持参しよう。
行きたい山によっては、山頂付近に山小屋やトイレがない場合があります。その際に携帯トイレが役立ちます。
用便が我慢できない場合は登山道から離れた安全な場所で、携帯トイレを広げて用を足すようにしましょう。防臭袋が付属していますのでしっかりと口を閉めて密閉して持ち帰り、お住まいの地区の処理方法に従って捨てましょう。
自分の地区では燃えるゴミで出すことができます。災害時にも役立ちますので、買っていて損はないと思います。購入はインターネットや登山用品店で購入できます。自分はモンベルの簡易トイレを持参しています。

【PR】
まとめ
登山も様々なマナーがあります。マナーを守ることで他人に迷惑をかけることなく、気持ちよく登山ができます。
一気に全てを意識して登山することは難しいと思います。少しづつ意識して、身につけていきましょう。
マナーを身につけて大自然を大切に登山をしましょう。ぜひ山での非日常を味わってください。あなたの安全登山を応援します!
- 登山保険に加入する。
- 登山計画を必ず提出する。
- レベルに合った登山をする
- ゴミは家まで持ち帰る。
- 汚水や残飯を捨てない。
- 植物や石などむやみに採取しない。
- 登山道から外れない
- 登山道をふさがない。
- 山のトイレは、ルールを守る。
- 早発ち・早着きを心がける。
- 登山中は周囲への配慮・注意を怠らない。
- 石を落としてしまったら、下に向かってすぐに声をかける。
- 登り優先・道を譲る際は山側で待つ。
- すれ違う登山者に挨拶する。
- 携帯トイレを持参しよう。
【PR】